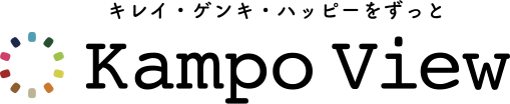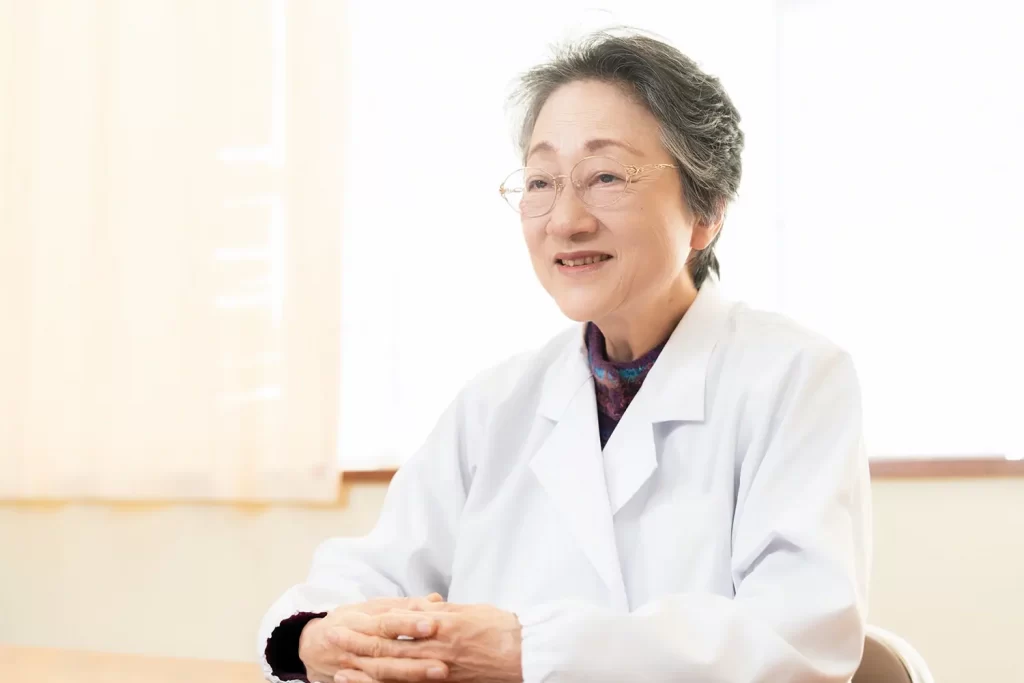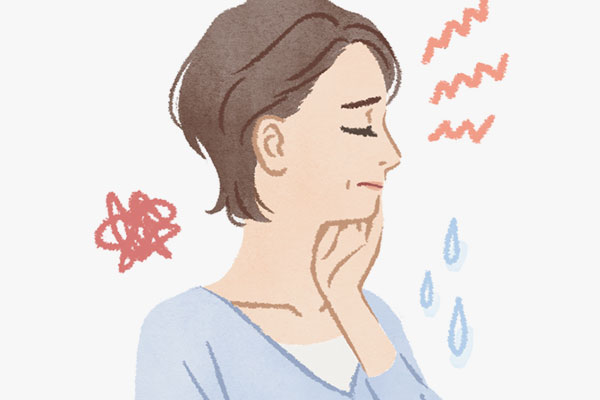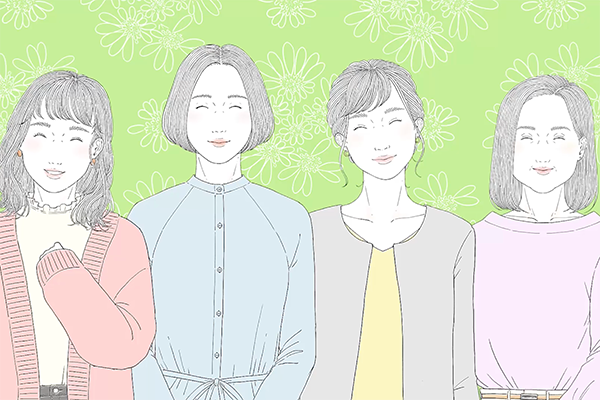女性のために目指した医療への道
〜更年期女性のために立ち上げた「おりひめの会」〜先生のプロフィール
医療法人社団 清心会 春日クリニック 院長 清田 眞由美 先生熊本大学医学部卒業。専門は消化器疾患、一般内科、更年期症状。1992年春日クリニック副院長、1997年同院長。1999年更年期の勉強会「おりひめの会」発足、2003年院内に熊本県初の女性外来を設置。日本女性医学学会専門医代議員、日本性差医学・医療学会評議員、日本東洋医学会専門医ほか。

2003年、熊本市内に初めて女性外来が設立されました。
立ち上げたのは清田眞由美先生。小さいころから「女性のために何か役立ちたい」という思いを大切に育て、更年期からの女性の生き方について、さまざまな角度から情報交換ができる場「おりひめの会」を1999年に始めた医師です。
なぜ清田先生は更年期、そして更年期以降の女性の健康に注目しているのか。ご自身が考える更年期からの女性の生き方や漢方の役割について、お話を伺いました。
「医師になると幸せになれない」と言われて

初めて「医師になること」を意識したのは、小学校に入る前でした。
もともと健康で、あまり病院にかかることはなかったのですが、それでも耳鼻科で何度か診てもらったことがあったんです。
その耳鼻科でいつも診てくれたのが、女性の医師でした。白衣姿でかっこよく、患者さんにはとても優しい。そんな頼れる姿に憧れを抱いたんですね。ただ、それは小さい子どもが「大人になったらパイロットになりたい」とか、「花屋さんになりたい」とか、そういったレベル。
何となく素敵だなって、思っていたぐらいだったと思います。
ですが、その後も医師になりたいという思いは消えず、女子校から地元の医学部へ。医師としての一歩を踏み出しました。
この間、頭の中にずっと消えずにいたのが、「女性って何?」という疑問でした。
最初に女性であることを意識したのは、中学生のときです。大好きだった女性の担任の先生から「女性は医師になると幸せになれない」と言われて、なぜ?どうして?と不思議に思ったんですね。その一方で、だんだんと女性と男性とは違うんだという感覚も出てきて、自然と〝女性のために何かしたい〟という意識が働くようになりました。
当時はまだ性差医療(女性と男性は体の仕組みが違うことを踏まえた医療)や、女性外来という言葉がなかった時代。そんななかで、モヤっとしながらも、「女性を診る医師になる」と考えていたことを覚えています。
衝撃だった「老人病院(療養型病院)」で見た光景
この「女性のために」という気持ちを強固なものにした出来事がありました。それは医師になりたての頃、某病院へ診療のお手伝いに行ったときのことです。
その病院は、昔でいうところの老人病院で、多くの高齢者が入院していましたが、その8割が女性だったのです。そして入院している高齢女性のもとに通って世話をしていたのは、40〜50代の女性(その娘さんもしくはお嫁さん)でした。
40代、50代というのはちょうど更年期に差し掛かる時期で、体調を崩しやすく、不定愁訴(※)が出やすい。それなのに自分の体調を顧みず、親の面倒を一生懸命みている女性たち。入院しているのも女性、その女性の世話をしているのも女性。とても衝撃的でした。
※なんとなく体調が悪かったり、さまざまな症状を自覚するにもかかわらず、検査をしても異常がみられない状態
もう一つ、大学病院で外来を担当していたときの出来事も、気持ちを後押ししましたね。
当時は更年期障害はあまり治療の対象になっておらず、更年期ぐらいの女性が不定愁訴で来られても、「なんでもないから、精神科に行ったらどう」などと言われてしまう。失望して帰る女性たちの姿を見て、自分が求めている〝女性のためにやりたいこと〟は、この人たちを救うことなのではないか?と気づかされたのです。
それ以来、子育てと内科の外来診療を両立しつつ、更年期医療や性差医療(女性外来)などについて勉強するようになりました。そこで出会ったのが漢方でした。
初めて実感した漢方薬の効果

じつは、初めて漢方薬の効果を実感したのは、研修医のときです。
風邪をこじらせて咳が止まらなかった女性患者さんに、「麦門冬湯(ばくもんどうとう)」を処方したところ、夜も眠れないほどの激しい咳が、2、3日で落ち着いたのです。漢方薬は(効果が出るまで)時間がかかると聞いていたのに、この効果には驚きました。
こんな経験があったことから、「西洋薬で治療が難しい時は漢方を使ってみよう」と思うようになりました。とはいえ、最初から漢方薬がうまく使えたわけではありませんでした。
漢方薬を学びたいから、当時は数少ないあちこちの勉強会に行きましたが、中医学と日本漢方の違いもわからない状況。漢方の複雑な診療体系だったり、何万通りもある生薬の組み合わせだったりを覚えるのはたいへんで、一筋縄にはいきませんでした。
それでも少しずつ「得意な処方」を広げていくことで、漢方薬を使う回数や種類が増えていったのです。ちなみに私の得意とする処方は、『女性三大処方』と呼ばれる、「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」、「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」、「加味逍遙散(かみしょうようさん)」です。「釣藤散(ちょうとうさん)」や「五苓散(ごれいさん)」「猪苓湯(ちょれいとう)」なども多用します。
加味逍遙散は私自身も服用している漢方薬です。イライラしたときに一服するとスーッと気持ちが治まります。スタッフもそれがわかっているみたいで、イライラしていると「先生、漢方!」と声がかかります(笑)。
「おりひめの会」と更年期症状を抱える女性たち
「おりひめの会」を立ち上げたのは1999年のこと。更年期からの女性の生き方について、さまざまな角度から情報交換ができる場で、インフルエンザやコロナウイルス感染症の流行期は除き、原則2カ月に1回開いています。
1回の参加者は30人ほど。毎回テーマが変わるため、2回、3回とリピートする人も多く、親子や夫婦で参加する人たちもいらっしゃいます。
クリニックを1992年に開業して以来、多くの更年期の女性たちを診てきました。開業当時は、更年期障害というと贅沢病とか、わがまま病といわれていた時代。患者さんに「更年期障害って言われると傷つく」と言われたこともあります。
更年期障害で生じる不調は200種類以上あるとされ、さらに周期的に変わる。これがまさに西洋医学で説明がつかず不定愁訴といわれる所以なのですが、それゆえ、コロコロ変わる自身の不調について医療者にうまく伝えられない女性も多く、診る側である医師も、毎回の診療で変わる訴えに困惑するという状態でした。
さらに、更年期の女性たちと接していると、女性ホルモンの低下という問題だけでなく、子育て、両親の介護、夫婦の関係、経済的な問題……といった多くの因子が女性に覆い被さっていて、それが心身の不調の根幹にありました。
母がこんなにつらい思いをしていたなんて……
これは医療だけで解決できるものではない――。そう思ったこともあり、クリニックには管理栄養士や理学療法士、ケアマネージャーなどもチームに加わってもらい、医療以外の部分のサポートもできるよう体制を整えています。
診療で得られたさまざまな話は、更年期の女性に共通するものでした。だとしたら、みんなで情報共有をしたほうがいいのではないかと思って、おりひめの会を始めたのです。
そんなおりひめの会で印象に残っている母娘がいます。
更年期に差し掛かっていたのはお母さんで、あまりの感情の起伏の激しさから、娘さんはうつ状態になっていました。そこで「2人で参加してみたらどう?」と、おりひめの会に誘ってみました。
2人が参加する会で、更年期について話を始めると、娘さんが突然、泣き出してしまったのです。そして、「母がこんなにつらい思いをしていたなんて知らなかった。私も将来そうなるかもしれないのに。母のことを大嫌いって思っていたことが申し訳ない」と話されました。更年期や更年期障害とはどういうものか、このとき初めて娘さんは理解されたのだと思います。
その娘さんも年齢を重ね、今は結婚して、時々ご夫婦でおりひめの会に来てくれています。そうやって親から子へ、子から孫へつながっていく会を開くことができるのは、とてもありがたく感慨深いことですね。
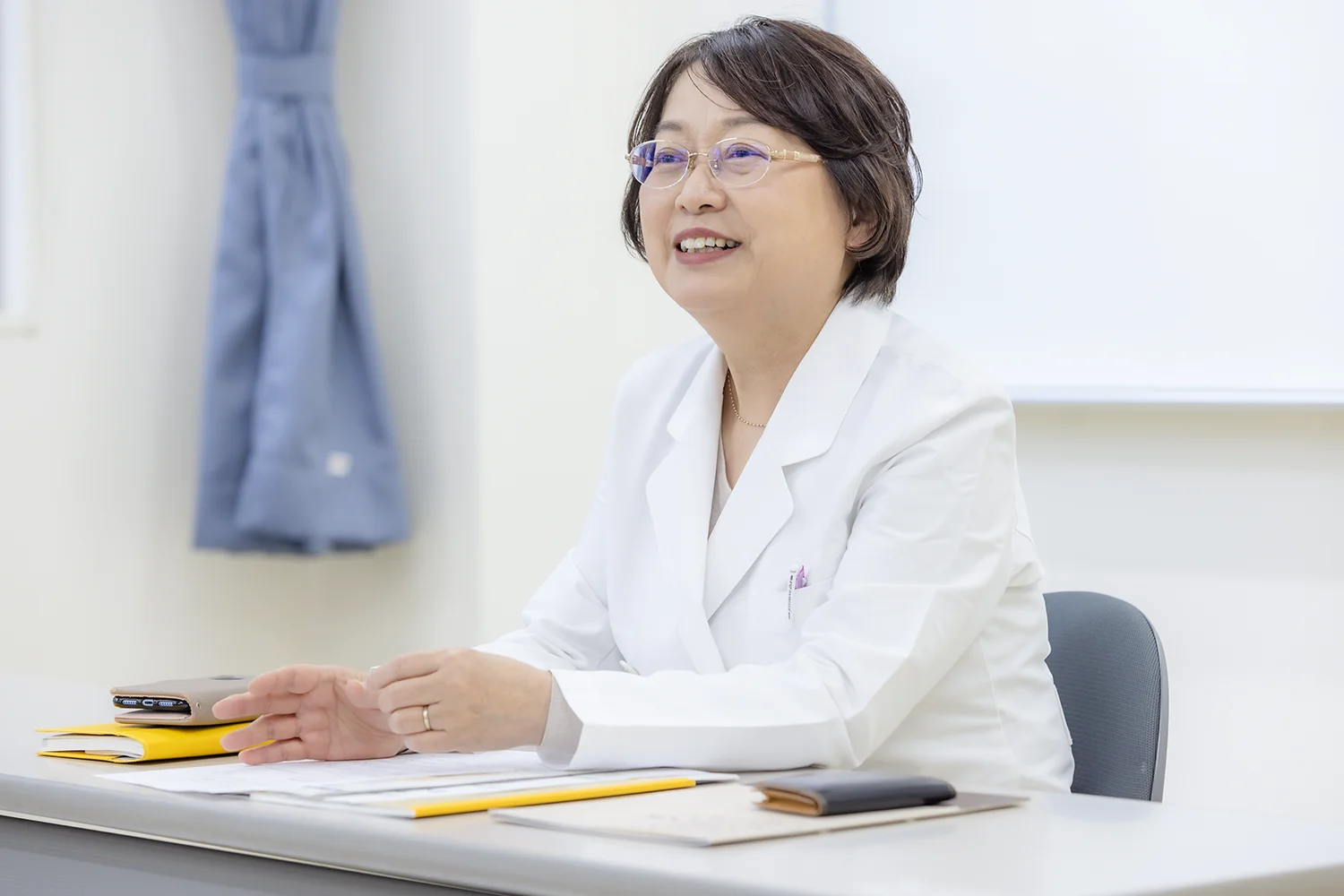
いつまでも健康で元気に過ごすために
私がおりひめの会を始めた頃と今とでは、更年期障害に対するイメージや、情報が格段に違います。自分の症状をネットで検索し、市販薬で対応するセルフケア、セルフメディケーションも一般的です。
ただ、「自分のことは、自分が一番わからない」ということも知っておいてほしい。
例えば、不調があって漢方薬を使う場合、症状をいろいろとネットで検索して、自分に合いそうなものを選ぶと思います。しかし、それが必ずしも自分にあった漢方薬ではなく、違う漢方薬に到達するかもしれません。
とくに更年期以降の症状は、表に出ているものが半分、残りは水面下に潜んでいます。だから、自身で選んだ薬を使っても体調に改善がみられなければ、やはり医師の元で相談されてみてはどうでしょうか。
最期まで健康で元気に過ごすためにも、更年期の過ごし方をおろそかにしてはいけません。女性であれば必ず通過する時期だからこそ、正しい知識をもって自分を大事にしていただけたらと思います。
※掲載内容は、2024年2月取材時のものです。