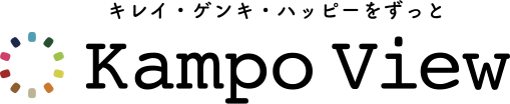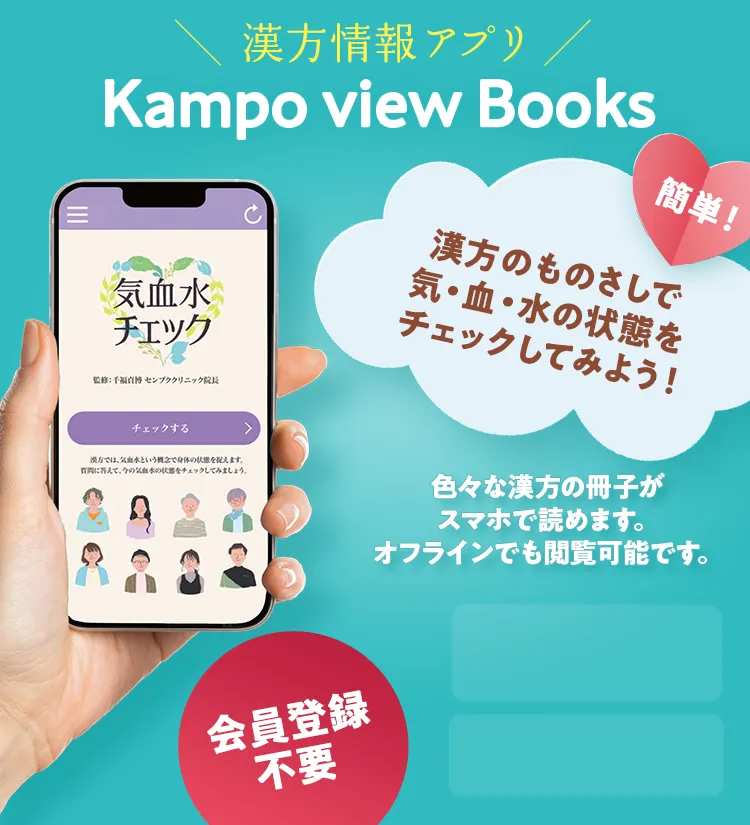今年の冬は万全な“冷え対策”を!

寒い季節になると、気になってくるのが“冷え”の悩み。
当然、気温が下がるので寒さを感じますが、じつは、人間はこの寒さには2週間程度で慣れるといわれています。
冷え対策は“カラダを冷やさないこと”が一番ですが、寒さに慣れないまま冬を越す人にとってはひじょうに辛いことです。
カラダが寒さに慣れる人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか?
今回は薬剤師である筆者が、冷えの原因と対策について解説します。
カラダが冷える原因と対策
一般的な冷え対策といえば“カラダを温める”ことなので、軽い運動をしたり、温かい食べ物や飲み物を摂ることが挙げられます。
では最初に、カラダが冷える原因とその対策を解説します。
1)自律神経の乱れ
ストレスや睡眠不足、生理前や更年期などのホルモンが不安定な時には、自律神経が乱れやすくなります。
その結果、カラダにもともと備わっている体温調整機能が正常に働かなかったり、血流量が抑制されることでカラダが冷えてしまいます。さらに、外気の寒さも加わることで、なおさらカラダは冷えてしまうのです。
良質な睡眠や、好きな音楽を聴いたり、半身浴、アロマオイルを活用するなどしてリラックスできるように心がけましょう。
2)基礎代謝の低下
人の一日の総消費エネルギーのうち、7割を基礎代謝が占めています。
したがって、基礎代謝を上げることは冷え対策として、とても大切なことなのです。
そもそもこの基礎代謝とは、生きていくために最低限必要なエネルギーのことで、筋肉や肝臓、腎臓、脳などさまざまなところで行われています。
この中で、意識的に代謝量を上げることができるのは“筋肉” です。つまり、筋トレや有酸素運動などは、冷えの改善につながると考えられます。
寒くなると、どうしてもカラダを動かしにくくなりますが、なるべくカラダを動かして熱を発生させるように心がけましょう。
また、肝臓や腎臓は冷えると代謝が低下しやすい臓器でもあります。
腹周りの冷えは内臓機能の低下を招き、基礎代謝の低下にもつながるため、腹周りを冷やさない努力も大切です。腹と腰の両方にカイロを貼って、内臓を冷やさない対策もオススメです。
冷えを放置するとさまざまな症状が…

冷えによって起こる症状は人それぞれです。
そして、冷え対策をせずにそのまま放置していると、さまざまな症状がカラダに現れてきます。
いくつか代表的な症状を紹介します。
免疫力が低下する
体温が1度低下すると、免疫力が約30%低下するといわれています。
また、リンパや血液の流れが悪くなり、カラダに老廃物が溜まりやすくなります。
頭の働きが鈍くなる
カラダが冷えて血流が悪くなると、脳の血流も悪くなります。
すると、頭痛を感じたり、やる気の低下、だるさを感じるようになります。
その他
肩こり、生理痛、吐き気、便秘、むくみ、イライラ、腰痛などさまざまな症状を引き起こすことがあります。
漢方薬が得意とする“冷え対策”

熱をつくる機能が落ちている冷え症の改善は、カラダの働きをよくして、症状を抑えていくことを目的とする漢方治療にとって得意とするところです。
漢方の考え方である「気・血・水(き・けつ・すい)」では、血が足りない状態(血虚)、血がとどこおっている状態(お血)、水分がたまっている状態(水毒)、気が不足している状態(気虚)などで起こるととらえます。また、いくつかの状態が重なって冷えが現れたり、悪化したりしている場合も少なくありません。
このように、冷えの原因はさまざまなので、処方される漢方薬もその人の症状に合ったものを選ぶ必要があります。ですから、自分で判断するのは控え、漢方に詳しい医師や薬剤師にそのときの体質や状態、他に現れている症状などを診てもらい、決めてもらうようにすると安心です。(※)
漢方ビューの「冷え症(冷え性)」ページでは、冷え症の考え方と代表的な漢方薬を解説しています。
冷え症というのは長い間に少しずつ進行してきた症状なので、短期間で症状がとれるものではありません。長い時間をかけて、改善をしていく必要がありますし、漢方薬の服用だけでなく、カラダが冷えにくい生活に改めることも大切です。
冷えは、「万病の元」といいます。
自分の“冷えている原因”を理解し、早めの対応を心がけましょう。前述の通り、漢方薬でもさまざまな症状に合わせたケアができます。冷え対策に「漢方薬」という選択肢も加えて、今年こそ快適な冬を過ごしたいですね。
※漢方の診察では、独自の「四診」と呼ばれる方法がとられます。一見、ご自身の症状とはあまり関係ないように思われることを問診で尋ねたり、お腹や舌、脈を診たりすることがありますが、これも病気の原因を探るために必要な診察です。
すべての医師がこの診療方法を行うとは限りません。一般的な診療だけで終える場合もあります。
ご存じですか?
医療用漢方製剤はお近くの医療機関で処方してもらうこともできます。
ご自身の症状で気になることがありましたら、一度かかりつけ医にご相談ください。
(すべての医師が漢方独自の診療方法を行うとは限りません。一般的な診療だけで終える場合もあります。)
こちらも参考に!
漢方に詳しい病院・医師検索サイト紹介
https://www.kampo-view.com/clinic薬剤師・大久保 愛