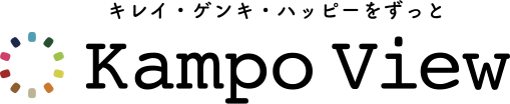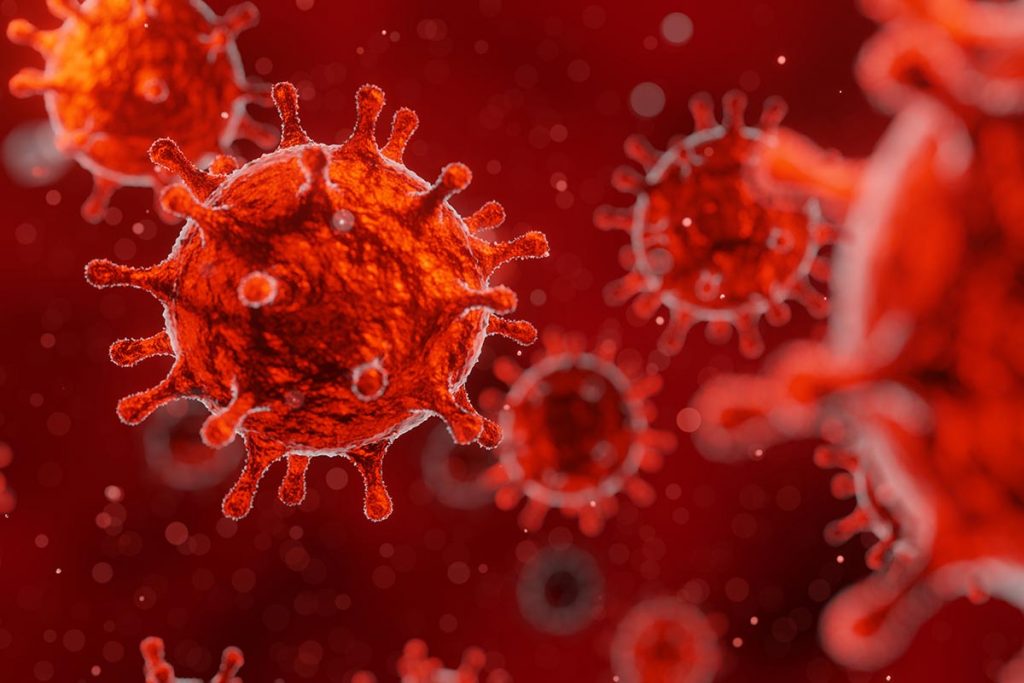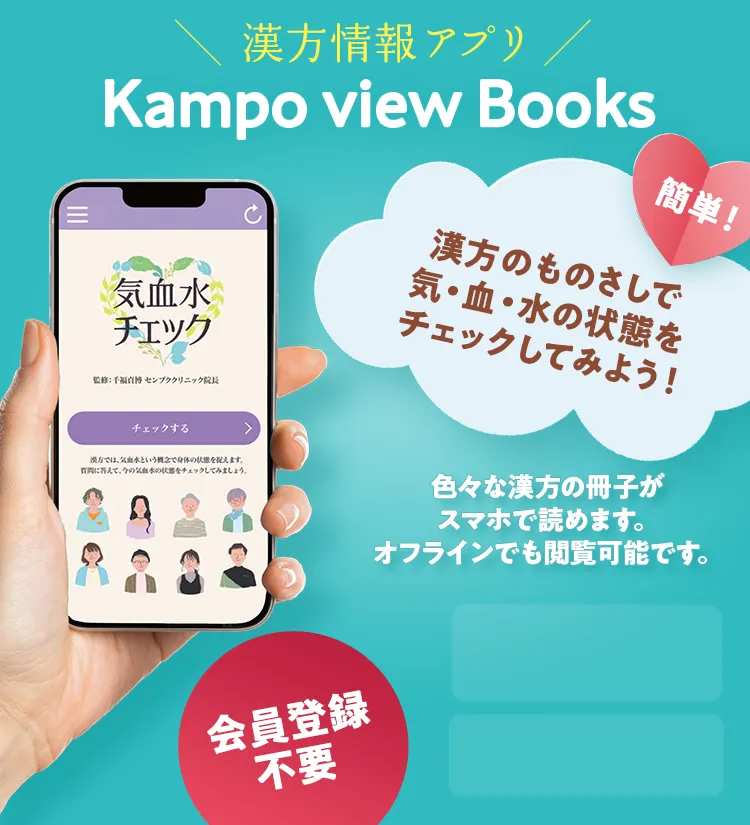警戒!秋から始まる感染症について

今年に入って新型コロナウイルスが流行していますが、例年だと、秋頃からウイルスなどによる感染症が増えてきます。理由は、秋になると低温・低湿度の環境により、インフルエンザウイルスなどが活発になるためです。
特に、季節の変わり目には、ウイルス以外のさまざまな不調にも気を付けなければなりません。
そこで、今回は薬剤師である筆者が、秋頃から警戒しておくべき感染症などについて解説します。
秋から冬にかけて流行する感染症
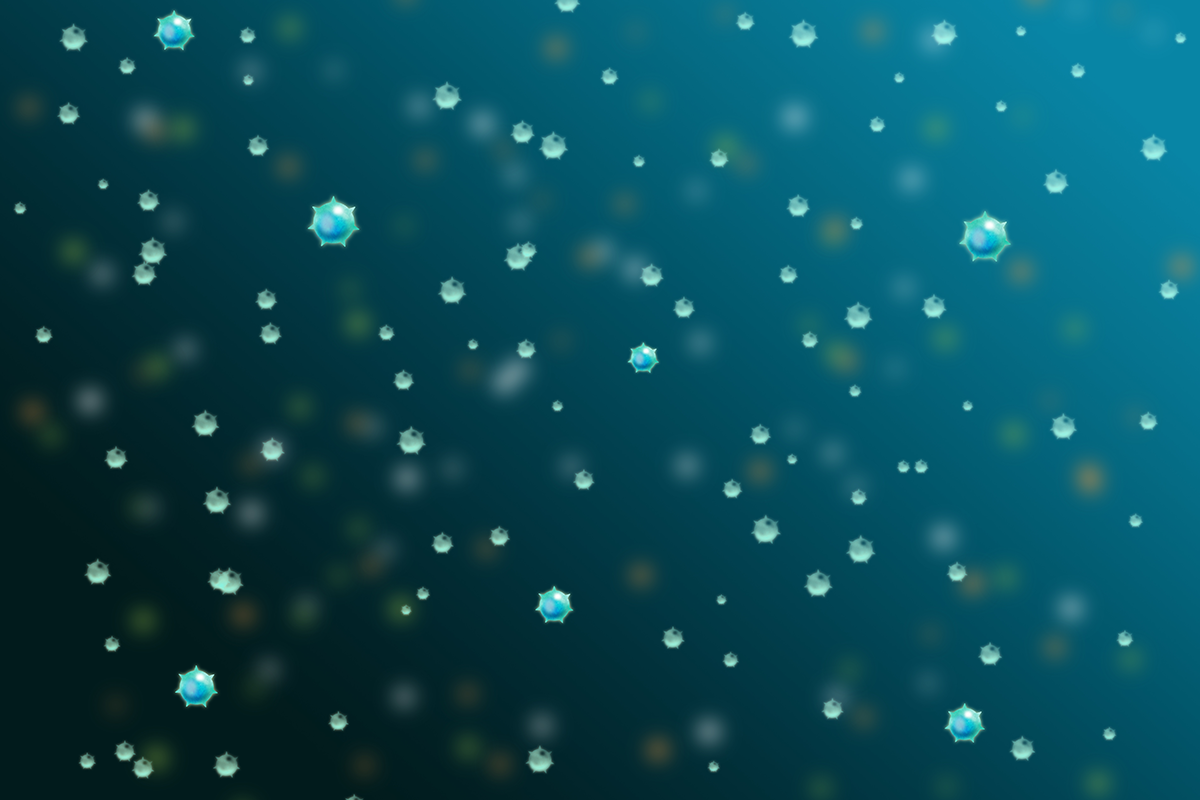
まずは、秋頃から流行しやすい感染症を確認しましょう。
<インフルエンザ>
感染力が強い代表的なウイルスです。症状としては、高熱、関節痛や頭痛等を感じます。
<胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルス)>
嘔吐や下痢、腹痛を感じます。嘔吐物の処理にも注意しなければなりません。
ロタウイルスについては乳幼児がかかりやすくなっています。
<食中毒>
肉や魚などに含まれる腸炎ビブリオ菌やカンピロバクターなどが原因となります。症状はさまざまですが、主に腹痛や下痢、嘔吐、発熱などが数日から2週間程度続きます。
<RSウイルス>
生後1歳までに半数以上の乳幼児が感染するウイルスです。咳や鼻水などの呼吸器系の症状を感じます。
<マイコプラズマ肺炎>
肺炎マイコプラズマという細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。症状としては、かわいた咳や発熱、頭痛などを感じます。小児や若い年齢層に比較的多く見られる肺炎の原因の1つです。
<溶連菌>
のどに感染して、咽頭炎や扁桃炎、それに小さく紅い発疹を伴う猩紅熱(しょうこうねつ)といった病気を引き起こします。小児に多い疾患で、発熱やのどの痛み、嘔吐などの症状があります。
感染症以外の不調にも注意

秋は季節の変わり目になるので、心身にさまざまな不調が出やすいとされています。
特に、夏からの疲れが残っていたり、薄着で生活をしていたりすると体調を崩しやすくなってしまいますので注意が必要です。
次のような不調に注意しておきましょう。
<気管支喘息>
気管支が狭くなることで、呼吸が苦しくなる発作を繰り返す病気です。季節の変わり目には、気管支喘息が悪化しやすくなります。
<花粉症>
春よりは症状が軽いといわれていますが、秋の花粉は気管に入って喘息のような症状を引き起こすケースもあるので注意が必要です。
<季節性うつ病>
温度変化や日照時間が短くなることなどにより、自律神経を乱し気分の落ち込みを感じることがあります。「意欲低下や思考が進まない」、「倦怠感がある」などの症状が出やすいとされています。
病気とはいえない不調には漢方を
感染症の基本予防は、「手洗い・うがい」そして「ワクチン」です。
それに対して、夏の疲れを引きずっていたり、季節の変わり目にカラダがついていかなかったり、冷えにカラダが負けてしまったりするような症状に対しては、特効薬のようなものが存在しないため、まずは“生活リズムの見直し”を心がけてみてください。
もし、それでも不調が長引くようであれば、病院へ。
また、前述した自覚できる症状以外の“病気といえないような不調”にも悩まされている方、「なんだか調子がおかしい・・・」だけでなかなか病院に行くことができなくて、ためらっている方も多いのではないでしょうか。
じつは、これらの不調は漢方の得意分野とするところでもあります。
漢方を得意とする医師に、自身の体調をしっかりと見てもらい、自分に合った漢方薬を処方してもらいましょう。同時に、少しずつで構わないので、生活習慣の改善も行えるとよいでしょう。

秋から冬にかけては、さまざまな感染症リスクや不調の可能性が考えられます。
何か違和感を感じた場合は、自己判断で済ませず、医師や専門家の判断を仰ぐようにしましょう。
的確な処置や対策を施すことで、自分の身はもちろん、周りの人たちにも安心を与えることができるでしょう。
ご存じですか?
医療用漢方製剤はお近くの医療機関で処方してもらうこともできます。
ご自身の症状で気になることがありましたら、一度かかりつけ医にご相談ください。
(すべての医師が漢方独自の診療方法を行うとは限りません。一般的な診療だけで終える場合もあります。)
こちらも参考に!
漢方に詳しい病院・医師検索サイト紹介
https://www.kampo-view.com/clinic薬剤師・大久保 愛